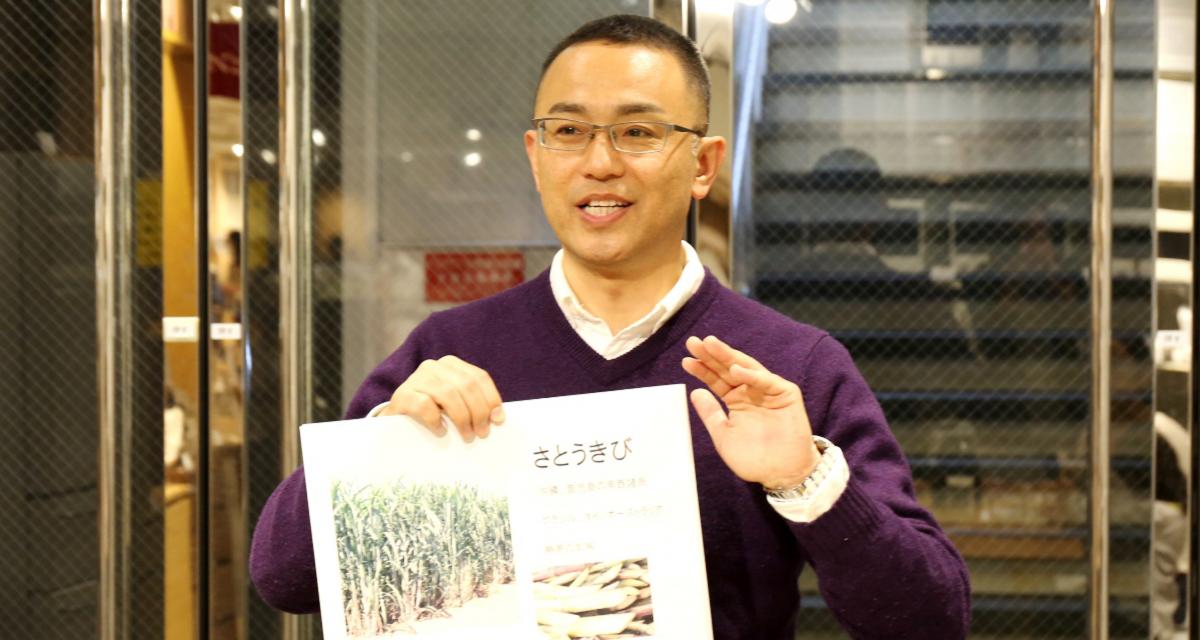和食の基礎調味料「さしすせそ」。「さ=砂糖」「し=塩」「す=酢」「せ=醤油」「そ=味噌」と、どれも身近な存在です。その一つ、砂糖業界に新しい風を吹かせ続けている人がいます。砂糖問屋「竹内商店」の3代目、竹内信一さん(50歳)。印刷会社から家業へ身を投じ、その奥深さを発信し続ける竹内さんの原動力とは?
かつて貴重品だった砂糖を現代に
スイーツというと洋菓子から和菓子まで、老若男女に広く愛され、進化も著しいものですが、その味の決め手である“砂糖”について詳しい人は、あまり多くないかもしれません。
「スーパーの砂糖売り場には哀愁が漂っている。そんな風に言われるほど、砂糖売り場は変化していない。業務用が大半を占める砂糖業界において、消費者向けの砂糖は進化してこなかったんです」
そう話すのは、昭和29年創業の日本橋にある砂糖問屋、竹内商店の3代目、竹内信一さんです。
確かに、塩や醤油、味噌などバリエーション豊かな調味料に対して、砂糖は上白糖、三温糖、てんさい糖など種類も少ない印象。そして、その違いについてもよく知られていないのが実情ではないでしょうか。
「かつて砂糖は希少な甘味として重宝されてきました。そして今も実は国の保護下にあるんです。だから業界が啓蒙する必要も、商品が変化する必要もなかったんですね」
江戸時代、鎖国中に唯一開かれていた港・長崎県の出島には、国内で採れた金銀との代わりに大量の砂糖が輸入されていました。当時、輸入に頼るしかなかった砂糖は貴重品として扱われ、庶民には手の届かないものでした。その名残からか、今も結婚式の引き出物などでは砂糖で象られた鯛の干菓子が贈られることもあるほどです。
「そんな貴重品として贈答されていたような砂糖を、現代に再現したいんです」
家業を継いだきっかけ
そう砂糖への想いを語る竹内さんも、元々は家業を継ぐつもりはなく、大学卒業後に入社したのは印刷会社でした。父親から継いで欲しいと言われることもないまま、様々な業界に関わることができる仕事に没頭し、気付いたら14年間勤めていたといいます。
しかし、ある時、父親が階段から転落。怪我をして仕事に支障をきたす父親を傍目に、たまたま会社で意気消沈する出来事とも重なり、今後の進路について悩んでいた竹内さんは一念発起します。家業である砂糖問屋を継ごう。
「そんな後ろ向きな決断だったので、最初の頃はキツかったですね。FAXで入る注文を処理していくだけの仕事。親父に問屋の付加価値って何なんだ?って聞いたら、『無理な納期に対応すること』と言われ、唖然としたのを思い返します(笑)」
ビルの一角の小さなオフィスで、毎日父親と肩を並べながら淡々と仕事をこなす日々。17時には仕事を終え、悶々としながら家路につくなか、砂糖問屋としての付加価値をずっと考え続けていたそうです。

新しい砂糖との出会い
そんな折、よしみにしている製糖メーカー「和田製糖」が、新しい砂糖を開発したという話が舞い込みます。それは、産地の異なるサトウキビから製糖された、茶褐色がかった砂糖。その内のひとつ、沖縄県産サトウキビから製糖された砂糖は、「“本”当に“和”の“香”りのする砂“糖”」で「本和香糖(ほんわかとう)」と名付けられていました。

「砂糖には白以外もあるのか!見た目もさることながら、味わいも香りも全く違う!」
白い砂糖というのは、サトウキビから抽出される原料糖から不純物を取り除き、極限まで糖分のみに製糖されたものですが、その砂糖は微量の蜜分とミネラルを残して製糖された含蜜糖(がんみつとう)といわれるものでした。
「その砂糖に可能性を感じずにはいられなかった。これだったら塩のように使い分けの提案もできるかもしれないと感じた」
という竹内さんは、和田製糖に対し、前職の印刷会社での経験を活かしながら、パッケージデザインや規格などを次々と提案していきます。しかし、取引の大半を業務用が占める和田製糖にとっては、手に負える話ばかりではありませんでした。
「ならば業務用を仕入させてもらって、自分たちのブランドとして自由に展開していこう。そして、一般消費者に向けて砂糖の奥深さを提案していこう」
そう考えた竹内さんは、砂糖問屋ならではの立場から、様々な砂糖を紹介していくオリジナルブランドを起ち上げるのです。ブランド名は屋号にちなんで、「MARUKICHI SUGAR」と命名しました。

砂糖の可能性の追求
まず、竹内さんが手掛けたのは、原料糖によって異なる砂糖をセットにした「キューブ」。自身が感動したように、砂糖ごとの風味の違いを、一度に楽しめる一品です。

初めは委託生産でスタートしたものの、発注ロットの少ない上に手間のかかる商品の生産は、なかなか引き受けてくれる先もありません。
「ならば、自由に商品開発できるよう自社工場を整備するしかない」
そう覚悟を決めた竹内さんの姿に、前職の元同僚たちが呼応し始めます。箱根でペンション経営を始めていた元同僚の鈴木清隆さんは、敷地の一角に工場を併設し、生産を担うことを快諾。

こうして父親と二人だった会社も、一人また一人と増えていき、企画から生産、営業までを一貫して担える体制が築かれていきます。
「日本で身近な砂糖といえば、調理に使うか、コーヒーに入れるスティックタイプが一般的じゃないですか。それが、フランスには様々な形をした砂糖があって、視覚から楽しめるんですよね」
それを知った竹内さんは、今度は成型された砂糖を企画。

コーヒービーンズやハート型の砂糖は、若い女性などからも「かわいい!」と人気を博し、オシャレなカフェなどからも引き合いが生まれました。
「一時、砂糖は悪者のような扱いをされていましたが、1g当たりのカロリーは小麦とほぼ同じ4kcal。さらにぶどう糖は、脳の重要なエネルギー源なんです。正しいことを伝えていくためには、見た目にも“かわいい”と感じさせる工夫が必要だと思っています」
そう話す竹内さんの将来の目標は、砂糖の発信源となるオリジナルショップを展開すること。
「ガラパゴス化してきた砂糖業界、やれることはまだまだある。悩みに悩んだ1~2年があったこそ今があると思っています。将来は誰かにこの事業を託せたらいいなと思うようになりました」
と語ります。最後に、そのモチベーションの源泉を聞くと、
「自分は砂糖のことを詳しく知らずにこの業界に入ってきたため、砂糖に対して新鮮な感覚で向き合うことができました。この感覚って、一般の消費者に近いと思うんです。意外と知られていない砂糖のことをもっと世に広めていきたい」
と答えてくれました。“灯台下暗し”という言葉があるように、その業界、その土地にずっと居ることで、その価値に気付きにくくなるものです。竹内さんのように、外からの視点で再発見する価値こそ、今の時代に必要なことなのかもしれません。